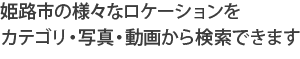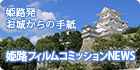メールマガジン
最新の記事
2007/12号
セピア色の風景と出会う、「昭和」を色濃く残した町
(高砂市高砂町)
姫路市の東隣にあたる高砂市高砂町。謡曲『高砂』で有名な高砂神社を中心に古くから開けた町で、特に江戸時代に入ってからは姫路藩の手で新たな港が築かれ、藩内の物産を積み出す集積港として発展を遂げ、併せて碁盤の目状の市街地が計画的に作られた。今でも碁盤の目状の町割りは健在で、次郎助町、細工町、北渡海町、魚町、船頭町といった昔ながらの町名が残り、そぞろ歩くとそこかしこで古い街並みと出会う。
たとえば高砂神社北側の堀川界隈は、江戸時代には年貢米を収める米蔵がぎっしりと軒を連ね、百間蔵と呼ばれていたところで、今も数棟の蔵が残り、往時の賑わいを偲ばせている。また、その西側の今津町には妻壁に舟板を使った堂々たる構えの民家や、扉が緑青色に輝く豪壮な蔵なども見られ、江戸時代にまで時代を遡らせるのは無理としても、「昔の面影をところどころに残した昭和の港町」ぐらいのイメージは引き出せる。
こうした昭和レトロを実感させる場所は他にも数多くある。北本町にある昭和7年に建てられた旧高砂銀行の洋館(現高砂商工会議所)や羽目板を巡らせた柔道場、まさに近代化遺産と呼べる栄町にある三菱製紙高砂工場のレンガ造りの建物群、魚町にある同社魚町倶楽部の異人館風の建物、藍屋町あたりで見かける“うだつ”が上がる商店、後でも触れる十輪寺の近くにある戦前から営業を続けている赤煉瓦煙突の銭湯などで、布製のアーケードがかかる次郎助町あたりの商店街も、どこか懐かしい昭和の匂いを色濃く残している。足の向くまま気の向くまま歩いていると、いろんなところでセピア色の風景と出会う、それがロケ地としてのこの町の魅力だと言える。
最後に紹介するのが町の西端に位置する十輪寺。寺伝によると弘法大師が勅命により創建し、その後鎌倉時代に法然上人が讃岐に配流される途中、この地に立ち寄り寺を中興し、浄土宗に転宗したと伝えられる名刹である。重厚な構えの山門、二層の屋根が美しい流線を描く本堂、本堂右手に続く大玄関、小玄関、庫裡は時代劇のワンシーンにも取り込めそうな荘厳かつ美しい佇まいで、ロケハンの価値は充分にあるだろう。
姫路へ行こう!今月の話題はこれ
HIMEJI Wintopia(ウィントピア)2007〜ひめじ、煌くとき〜
日ごとに寒さが厳しくなってきましたが、そんな中でも、皆様に、中心市街地へ足をお運びいただいて、心を温まっていただこうと、地元の商店街等の団体が中心となって、姫路の街を様々なイルミネーションで彩る「HIMEJI Wintopia2007」が開催されています。
普段、夜の商店街では早くお店が閉まり寂しくなりますが、この時期はイルミネーションや光のオブジェなどを飾り華やかになります。
商店街のアーケードを光り輝かせたり、公園に、地元の小学生たちが「銀河鉄道の夜」をテーマに作ったステインドグラスを飾ったりしています。
開催期間は、平成20年1月14日までですが、一部では、12月22日までとなっております。
皆様のお越しを是非お待ちしております。